第12回:北川 雄光 教授
慶應義塾大学病院臨床研究推進センターは、最先端の医療を実現すべく、2014年に開設されました。いかなる使命の下、何を目標とし、日々どのような課題と向き合っているのか。同センターの広報部門長・大家基嗣(おおや・もとつぐ)が、臨床研究の現場に携わる教授陣をリレー形式でインタビューします。
大家基嗣によるリレーインタビューの第12回。慶應義塾大学病院 病院長の北川 雄光(きたがわ・ゆうこう)教授をゲストに、外科治療から見る臨床研究、最新がん治療への取り組み、次世代リーダーの資質について聞きました。
Profile
北川 雄光 教授慶應義塾大学病院・病院長
慶應義塾大学医学部外科学教室・教授
大家 基嗣 教授
慶應義塾大学病院・副病院長
慶應義塾大学病院・臨床研究推進センター・広報部門長
慶應義塾大学医学部泌尿器科学教室・教授
外科治療における臨床研究の難しさ
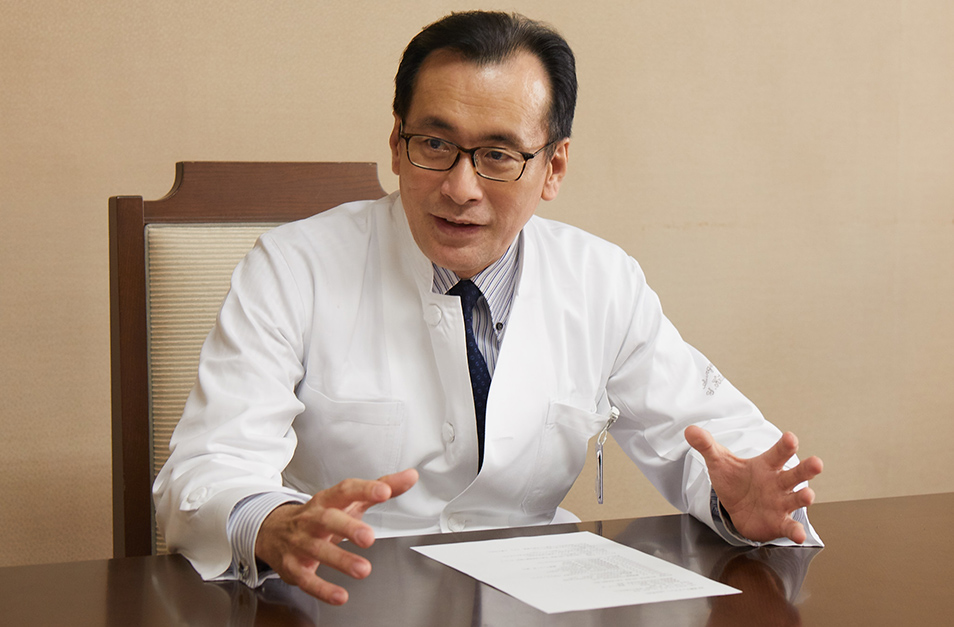
大家教授(以下、大家):今回は病院長の北川 雄光教授にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
北川教授(以下、北川):よろしくお願いいたします。
大家:北川先生は、慶應義塾大学病院の病院長であると同時に、外科、特に食道外科のご専門家でいらっしゃいますね。食道外科を選ばれたのは、どのようなきっかけですか?
北川:まず外科医になったきっかけの一つは、がんに興味があったことです。私が医学部を卒業した1980年代は、固形がんの治療のほとんどは、外科系の医師が行っていました。あまり良い抗腫瘍薬剤もなかったですからね。特に消化器がんに興味を持って、外科に入りました。食道・胃などの消化器外科の中でも、上部消化管がんが私の専門です。食道がん手術はとても大きな手術なので、当時は、多くの患者さんが、術後集中治療を要していました。
大家:北川先生は、初期研修時代、救急のメッカと言われていた済生会神奈川県病院にいらしたそうですね。
北川:はい、そうです。済生会神奈川県病院で、たくさんの熱傷や外傷の患者さんと接しているうちに、自分は集中治療に興味があることに気づきました。当時の日本では、まだ生体肝移植が始まっていませんでした。食道がんの分野では、進行がん患者さんの命を救うために、あえて手術侵襲を与え、根治切除する治療法が行われていました。それで食道グループに所属したという経緯です。

大家:若い頃から、チーム医療や長時間の手術、集中治療など、いわゆる最も外科らしい分野にご興味があったのですね。困難な治療にハイモチベーションで臨んでこられたのが伝わります。過去のリレーインタビューで伺った臨床研究の事例は、主に薬物治療の研究が多かったのですが、外科治療における臨床研究には、どのような特徴があるのでしょうか。
北川:一言で申し上げると、外科手術のエビデンスをつくるのは非常に難しいです。今、標準治療と言われているものでも、それを裏付ける論文がないものもあります。それまでの外科治療のエビデンスを構築するための議論を深めたのが、1990年代の胃がんに対する予防的リンパ節郭清の研究です。日本の外科医がオランダで、ヨーロッパの外科医とともに、ヨーロッパの患者さんを対象に2群までのリンパ節郭清(D2, がんおよび、がんの周辺にあるリンパ節を切除すること)と1群のみのリンパ節郭清(D1)の比較を行ったのですが、これがまさに外科手術に関する臨床試験における諸課題が浮き彫りになる契機になりました。
大家:詳しくお聞かせください。
北川:当時、日本では、きちんとリンパ節郭清(D2)を行うことで胃癌術後の予後が改善すると考えられていました。ところが、ヨーロッパでこれを検証した研究では逆の結果が出てしまったのです。リンパ節郭清を大きくすればするほど、合併症が発生して、予後が悪くなるという結果が出たのです。しかし、実はそれは、経験値の少ない外科医が、十分標準化されていない方法で手術を行うと、拡大手術はむしろマイナスになる、という教訓でした。その後、長期経過を追ってみると、合併症で亡くなった方は別として、きちんとリンパ節郭清をおこなった方のほうが、がんの死亡リスクは少ないということがわかり、今では、欧米でも日本式のリンパ節郭清が標準治療としてガイドラインに記載されるようになりました。このように外科系の臨床研究は、どのように手技を標準化し、一定の技術を持った人がそれを証明していくか、等の課題があり私たち外科医はまさに試行錯誤しながら臨床研究に取り組んできました。
JCOGの一員として進める、最新がん治療への道
大家:北川先生は、JCOG(日本臨床腫瘍研究グループ)の食道がんグループの代表も務めていらっしゃいますね。

北川:はい。JCOGでは外科手術の臨床試験を世界に先駆けて、数多く手がけています。例えば、胃がんグループでは、日本のお家芸ともいえる胃がんの手術(D2)をさらに拡大すれば、予防的リンパ節郭清で予後を良くできるのではないかと、さまざまな臨床試験に取り組まれてきました。しかし、リンパ節郭清の程度をさらに大動脈周囲まで拡げたり、食道に浸潤した胃がんに対して左開胸を加えてリンパ節郭清を行ったり、あるいは胃全摘の際に脾臓を摘出しても合併症や出血量、手術時間が増えるだけで予後は改善しないということがわかりました。その結果、外科手術には、適切な局所制御範囲があることが明らかになり、近年ではこれをより低侵襲な手術で行う方向に発展してきました。術後の生存率が同じであれば、身体に優しく、回復の早い低侵襲手術が推奨されます。私たち食道がんグループも、今、食道がん手術において、開胸手術と胸腔鏡手術のどちらが本当に安全で、どちらが良好な生存率に寄与するかという比較試験をしています。現時点の標準的な手術は開胸手術ですから、胸腔鏡手術でそれに劣らない長期成績が確認できるかを検証しています。
大家:開胸手術か胸腔鏡手術か、はランダム化(無作為化)されますか?
北川:ランダム化します。世界では、まだはっきりとした結果が出ていませんので。
大家:私も泌尿器科という外科系診療科の一員として、手術のランダム化については、いつも悩ましく思っています。例えば、腎臓がんで全摘するか、部分切除するかという場合に、倫理的な問題などもあり、手術のランダム化の同意が得られず、結局レトロの分析とメタ解析に終わってしまい、結果が出ないということもあります。ランダム化できた場合でも、術式の標準化が不十分なため、施設間の格差が大きく出てしまい、治療成績が悪くなってしまう場合もあります。手技の標準化は一番のポイントになりますね。
北川:比較する二つの術式が非常に似通っている場合も、適切なランダム化比較試験を行うことが難しくなります。例えば、リンパ節郭清の範囲を第1群リンパ節まで行うか、第2群リンパ節まで行うか、を比較する臨床試験としましょう。この場合、第1群リンパ節の郭清までに留めるべき症例に対して外科医が、ついつい頑張りすぎで第2群リンパ節まで郭清してしまうこともあります。一方、第2群リンパ節までの郭清を行うべき症例に対して外科医の手技が稚拙で1群リンパ節郭清に留まってしまう場合もあります。術式が似ていると、このようなことが起きる可能性があります。むしろ脾臓をとるかとらないか、開胸するかしないか、といった術式の差が明確な試験のほうが、ランダム化はしやすいですね。一方で別の問題もあります。比較する治療法があまりに異なると、患者さんがランダム化に抵抗を感じる傾向があります。私たちは、食道がんの患者さんに対して、切る治療つまり手術と、切らない治療つまり化学放射線療法の二つを比較するランダム化試験を行いましたが、ランダム化同意率が極めて低いことが予想されましたので、ペイシェントセレクション(患者さんが治療を選択)で行ったデータも集積することになりました。このように薬剤とは異なり、外科手術をランダム化比較することの難しさを感じています。
大家:おっしゃるとおりですね。
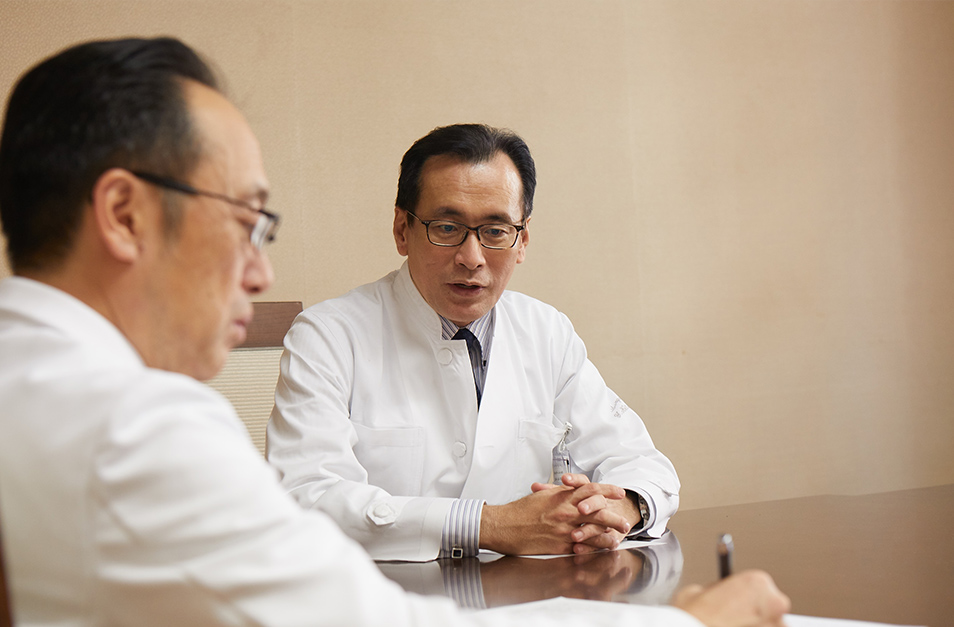
北川:先ほどお話しました胸腔鏡手術と開胸手術の臨床試験も、ランダム化比較試験(RCT)を行なっていますが、胸腔鏡手術のような新しい治療法が出てきたときに、どのタイミングでRCTを行うかも難しい課題の一つです。新しい治療法が出始めたばかりの段階でRCTを行うと、手術の習熟度が足りない施設のデータが入ってしまう可能性があります。すると、将来性のある治療法にも関わらず、そこで否定されてしまう可能性があります。しかし、RCTの実施時期が遅れると、その新しい治療法がエビデンスのない状況で普及してしまい、RCTそのものが成り立たなくなってしまいます。新しい手術手技のRCTは、それを行う適切な時期があることが大きな特徴と言えます。
大家:タイミングの見極めが非常に難しいですね。
北川:そうですね。また、食道がんはいろいろな治療法がありますので、放射線治療も化学療法も手術も、一つでは治療として成り立ちません。私たちJCOG食道がんグループでは、これら3つを合わせた集学的治療に関する臨床試験を多岐にわたって行っています。様々な専門家が集まって協力しますので、臨床研究としてのモチベーションを高めやすいですね。
大家:食道がんは、がんの中でも集学的治療がもっとも取り入れられている印象がありますね。
北川:日本の場合、食道がん手術の黎明期は別として、一定の術式が確立した後は手術による局所制御が優れていたので、切除可能な食道がんに対して放射線治療をあまり取り入れてきませんでした。しかし、欧米ではもう20年前から化学放射線療法を食道がん集学的治療の中心に置いています。最近では、日本でも進行食道がんの治療成績をさらに良くするにためには化学放射線治療やより強力な化学療法も導入した上で外科手術を加える、という発想が出てきています。現在これについてもJCOG食道がんグループで臨床試験を行なっています。
大家:同じがんへのアプローチでも、泌尿器科は、食道がん、胃がんとはかなり違うと感じています。一番顕著な例で言いますと、腎臓がんです。リンパ節転移しないので、昔は郭清していたのですが、合併症も多く治療成績はあまり変わらないので、今は画像上見つからなければ郭清しないのが原則です。一方、膀胱がんは郭清したほうが成績はいい。これは消化器のがんによく似ています。また前立腺がんは、リンパ節の転移とは別にそれとは異なるクローンが骨に移動するので、リンパ節を郭清しても意味がありません。ゲノム解析が進んだ結果、がんによって、それぞれ性質が異なることがわかってきました。いわゆるがんの不均一性、Heterogeneityですね。
北川:大家先生がおっしゃるようなHeterogeneity、特殊な転移形式をとるがんは、消化器でもあると思います。ただし、食道がんの例で言うと、圧倒的にリンパ行性転移が多い。リンパ行性転移で最終的に患者さんの命を奪うという頻度が高いです。胃がんの場合は腹膜播種ですね。消化器官の中でも、いろんな転移再発形式がありますね。
大家:JCOGのたゆまぬ努力や、これまでの知見を生かした最新の取り組みは素晴らしいですね。大変勉強になります。
がんゲノム医療中核拠点病院として、がん治療の個別化を牽引したい
大家:慶應義塾大学病院は2016年、竹内 勤病院長の時代に臨床研究中核病院に認定されました。昨年(2017年)に北川先生が病院長に就任され、さらに今年2月16日付けで「がんゲノム医療中核拠点病院」に選ばれたわけですが、「がんゲノム医療中核拠点病院」について教えて下さい。
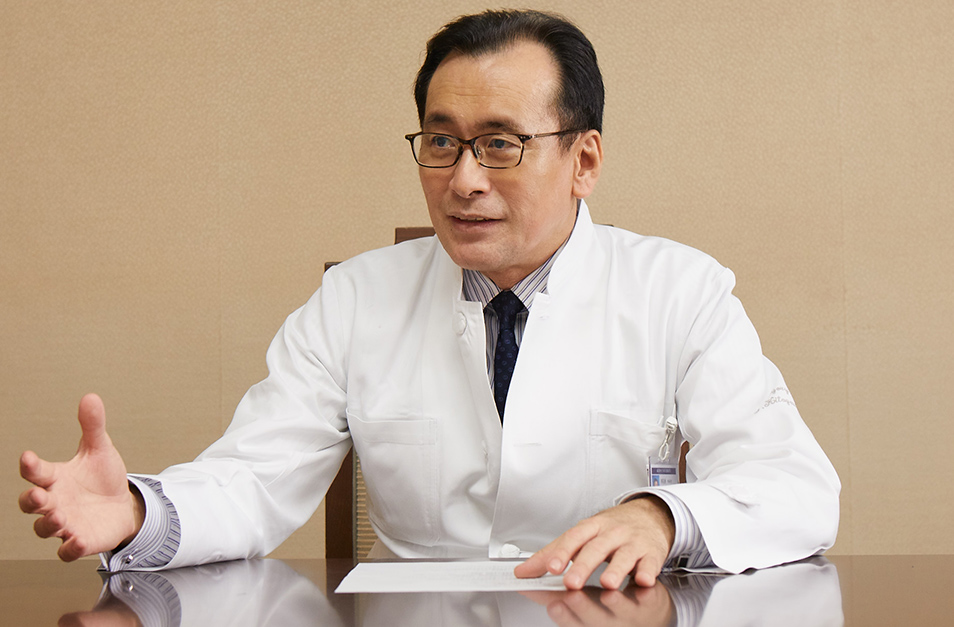
北川:「がんゲノム医療」は、がんの原因や悪性度を規定している体細胞の変異を調べ、適切な薬剤を同定し、治療に生かすという、非常に精密で個別的な医療を目指した取り組みです。欧米で先行しており、日本としても国を挙げてこれを推進しようという機運が高まっています。最終的には、国立がん研究センターにがんゲノム情報管理センターを置き、日本のがん患者さんの遺伝子変異データを集め、臨床データと付き合わせながら、希少がんや難治がんなどの原因を究明したり、一般的に多く見られるがんについては治療の個別化をはかったりすることを視野に入れています。その中心となって機能を整備していくのが「がんゲノム医療中核拠点病院」で、連携施設と一緒にこの施策を推進する役割を担っています。
大家:これにより、患者さんにはどのような変化が生まれるのでしょうか。
北川:現在のがん治療においては、エビデンスに基づいて策定された診療ガイドラインに基づき、それぞれの臓器がんの進行度に合わせた標準治療が選択されています。その中で、もうガイドラインで推奨される標準治療がないという患者さんに対して、新たな治療法を探るために特殊な検査としてゲノム検査を行っていました。これからは、一般の進行がんの患者さんに対して、最初から手術検体を培養バンクに保存して遺伝子パネル検査を実施し、術前治療や再発後の一次治療の段階から個別化する時代に入ると思います。この臓器のがんにはこの治療というだけの標準治療の時代は終わり、近い将来、全遺伝子検査に基づく個別の治療体系をつくることが標準になっていく。その取り組みが、今まさにスタートしたところです。
大家:それが実現したら、完全なパラダイムシフトが起きますね。今のがん治療の個別化は、ほんの一部の患者さんに対して適応されているような状況ですが、すべての患者さんが対象になる時代が来るということですね。
北川:はい、そのとおりです。慶應がぜひこの分野を先導したいと考えています。
科を越境し、治療全体を俯瞰できる人材が、次世代リーダーとなる
大家:北川先生は、あえて非常に困難な道を選んでここまで歩んでこられた医療人という印象を受けます。ご経験を踏まえて、若い先生方、次世代を担う医療人へのメッセージをお願いします。
北川:私自身のことを少し振り返りながらお話しましょう。私の所属するJCOG食道がんグループでは、安藤暢敏先生(現国際親善総合病院 病院長)が先代のリーダーを務めていらっしゃいました。ですから私は、若い頃から安藤先生のもとでJCOGの会議に参加し、外科医だけでなく腫瘍内科や放射線科、生物統計家の先生達と非常に厳しいディスカッションを重ねる機会に恵まれました。その経験を通じて、臨床研究、臨床試験はどのような手法で組み立てていくのか、どうあるべきなのかという概念が自然と身につきました。現在、治療にあたる時も、この時の学びが生きています。自分の本職は外科医ですが、腫瘍内科や放射線科、生物統計家の思考を理解しながら、一緒になって、チームとして治療にあたっているのです。がん治療は、決して単一の診療科で完結するものではありません。ですから、今の若い外科医の先生がたには、早くからチーム医療に取り組み、チームで研究する体験をしてほしいですね。この体験は、将来チームのリーダーになるためにも必須だと思います。

大家:北川先生は、がんプロフェッショナル養成コースもご担当されていますね。どのような体験ができるプログラムなのでしょうか。
北川:このプログラムで非常に優秀な人が育っています。彼らはこのプログラムを通して、外科医でありながら、その他の診療科、例えば放射線科や緩和医療、病理、泌尿器科、血液内科などもローテーションし、経験を積みます。がん治療の全体像を俯瞰する力をつけた上で、最後に自分の得意技である外科医としてのスキルを磨くという修練を積んでいるのです。最近では、消化器外科専門医と腫瘍内科のがん薬物療法専門医を同時に取れるような若手も出てきました。そういう人が、次世代リーダーとして集学的治療時代を引っ張る人材になると思います。もちろん外科医でなくとも、さまざまな分野に関わる人たちが、そういうトレーニングを受けてほしいですね。
大家:実にうらやましいお話です。私が若い頃は、そのようなプログラムはほとんどなかったです。臨床研究推進センターでは、さまざまな教育講座を設けていますので、ぜひ若いうちから受講し、臨床研究とはこういうものだ、という実感を得ていただければと思います。日常のカンファレンスで出てきた疑問を、臨床研究の手法を使って解決するといったスタディを組むことも可能だと思いますので、ぜひとも若い先生方には挑戦していただきたいです。
北川:若いうちの成功体験が、その人の将来に、大きな良い影響を与えると思うので、臨床研究推進センターには、若手のモチベーションを上げるような活動をぜひお願いしたいです。若手が臨床研究に入っていけない心理的障壁が、きっとあるのだと思います。例えば、臨床研究法の施行によって、臨床研究の実施基準が非常に厳しくなりました。ともすると、若い人たちが萎縮する状況にもなっていると思います。慶應義塾大学病院は、臨床研究を牽引する臨床研究中核病院であり、その中心が臨床研究推進センターですので、アクセルとブレーキの両方を効かせながら、うまく若手を守り、育ててほしいという気持ちです。
大家:本当にそうですね。
北川:どんなことをしたら自分が臨床上で抱く疑問(クリニカルクエスチョン)を解明できるか、という具体的な手法を教えていただく積極的なサポートも期待していますし、大きな踏み外しをしないよう、ここは守らなければいけないというブレーキ機能にも期待しています。アクセルとブレーキをバランス良くかけていただくことで、若手が安心して臨床研究に取り組むことができるようになると思います。
大家:ぜひご期待に添えるようにしたいと思います。本日はありがとうございました。
対談後記

大家先生とお話し、あらためて私自身の経験を振り返ったときに、若い世代の先生方には、早い段階から、診療科の枠を超えて、様々な分野の専門家の方と切磋琢磨する機会を持って欲しいと感じました。がん治療が集学的治療の時代になっているように、今後患者さんを中心とする医療の進歩に向けて、より総合力が求められる時代となってくると思います。ご自身の医療技術を磨く傍ら、是非臨床研究やサポートプログラムへ積極的に参加し、視野を広げていってほしいと思います。今回は、インタビューにお招き頂き有難うございました。
北川 雄光 教授

今回インタビューをさせていただいて、北川先生はそれこそ若いうちから、外科医としてより困難な道を自ら選択されて、がん治療を向上させてこられたのだと本当に頭が下がる思いでした。今年から新しい病院が稼動し、臨床研究法の施行やがんゲノム中核拠点病院としての役割への対応等、引き続きさまざまな改革が求められる状況と思いますが、北川病院長のリーダーシップのもと、我々センターもより一層努力を重ねていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
大家 基嗣 教授
