第5回:竹内 勤 教授
慶應義塾大学病院臨床研究推進センターは、最先端の医療を実現すべく、2014年に開設されました。いかなる使命の下、何を目標とし、日々どのような課題と向き合っているのか。同センターの広報部門長・大家基嗣(おおや・もとつぐ)が、臨床研究の現場に携わる教授陣をリレー形式でインタビューします。
大家基嗣によるリレーインタビューの第5回。慶應病院の病院長である竹内勤(たけうち・つとむ)教授をゲストに、日本における臨床研究のこれまでとこれからについて聞きました。
Profile
慶應義塾大学医学部内科学教室(リウマチ)・教授
慶應義塾大学病院・臨床研究推進センター・広報部門長
慶應義塾大学医学部泌尿器科学教室・教授
※所属・職名等は取材時のものです。
日本で臨床研究が進まなかった理由
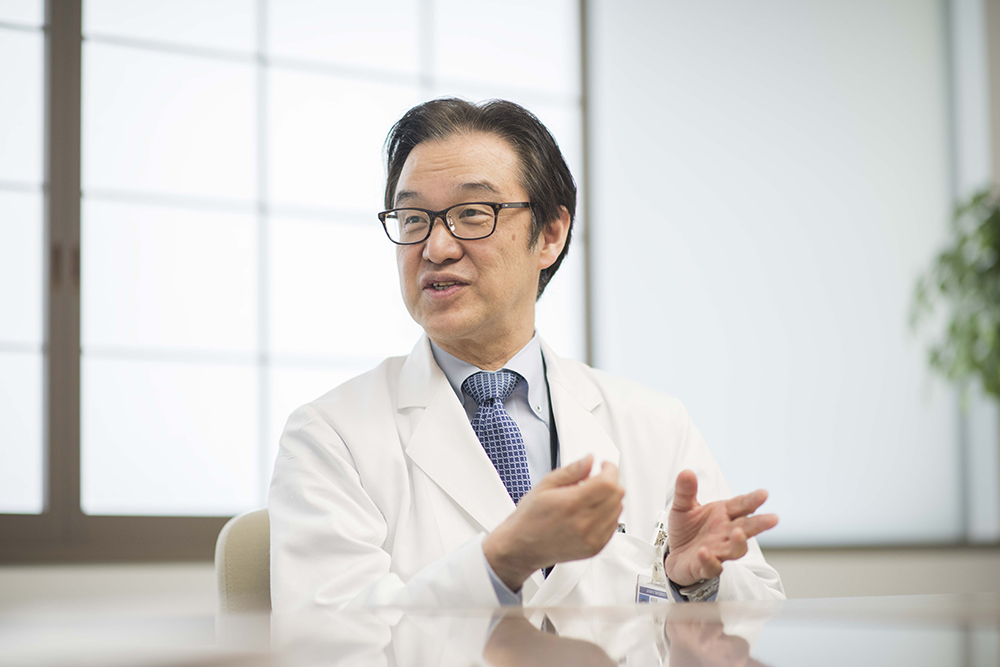
大家教授(以下、大家):慶應病院の病院長、竹内勤教授にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
竹内教授(以下、竹内):よろしくお願いいたします。
大家:慶應病院は、今年3月25日付で医療法に基づく臨床研究中核病院に承認されました。
竹内:臨床研究中核病院とは、日本発の革新的な医薬品・医療機器・医療技術の開発に必要な質の高い臨床研究や治験を推進するため、国際水準の臨床研究や医師主導治験の中心的役割を担う病院として、厚生労働大臣が承認するものです。2015年度から施行され、私立大学病院としては慶應病院がはじめての承認となります。臨床研究を自施設でもきちんとすることができ、他施設の支援もすることができる設備や環境、人材が整っていることを国から認められた、ということでもあります。
大家:承認病院しかこの名称を使えないということで、かなり重みをもった位置づけですね。
竹内:世界の医学研究、生物学研究において、日本は、基礎医学に関しては非常にたくさんの成果を上げており、評価もされています。一方、臨床研究においては、クオリティの高い論文は少なく、本数も多くない。それが特に近年顕著になっていました。これは、研究成果が少ないという問題だけでなく、大学での研究成果が患者さんに還元されていないという問題にも通じます。実際、国内の基礎研究で非常に重要な発見がなされても、それを応用した新薬開発は海外メーカーが手がけ、そうしてできた新薬が逆輸入されて、日本の患者さんに使われるということが現実に起きているのです。はたしてそれは適切なのか、ということですよね。
大家:確かに、おかしな現象です。
竹内:そういう流れができてしまっているのは、私たち医師にも原因があります。長らく医学界では、アカデミアがやるべきは基礎研究で、基礎研究が済めば、私たち医師の研究は完結すると捉えられていました。基礎研究こそが医学系研究の中で最も重要だと言われていて、臨床研究は"付けたし"のような存在と見なされていて、臨床研究をしても評価されにくい状況にありました。でも、それがそもそも間違いなんですよね。国もそれを感じ取り、臨床研究の大切さを改めて認識し、このような中核病院の取り組みを進めているのだと思います。
大家:そうですね。私は、海外に比べて日本の臨床研究がなかなか進まない背景には、医学界の構造的な違いも影響していると感じています。日本は小規模な病院が乱立していますが、海外は地域に大きな病院がどんとあり、その上で開業医さんがいます。これは大きな差です。例えば、ある臨床研究を他施設と共同で行う場合、おそらく欧米ではその試験の被験者を集めるために、少数の病院で必要な症例数をまかなうことができます。一方日本では、非常にたくさんの施設から集めなければならず、その分、試験のクオリティも落ちやすくなります。
これに加え、竹内先生が指摘した、臨床研究が医師の中で重視されていなかったという問題ですよね。研究をして学位をとったらおしまい、あるいは学位を取得した後も一生懸命研究しているのだけれど、論文を書いたらおしまい。それでは進みようがありません。
竹内:臨床研究の重要性が認識されていなかったのは、日本の文化や風土の影響もあると思います。臨床研究や治験といった新しい薬を試す行為は、人体実験のようで悪いことだ、というような認識が日本社会にはありました。私たち医師も、その必要性を十分に説明してこなかったですし、社会もそれをきちんと受け止めてこなかったのだと思います。しかし、それでは医学は進歩しません。進歩のためには、新しい薬や新しい医療技術が必要なんですよね。そのためには、臨床研究が欠かせません。その視点が、今までは不足していましたよね。
臨床試験における日米の違い
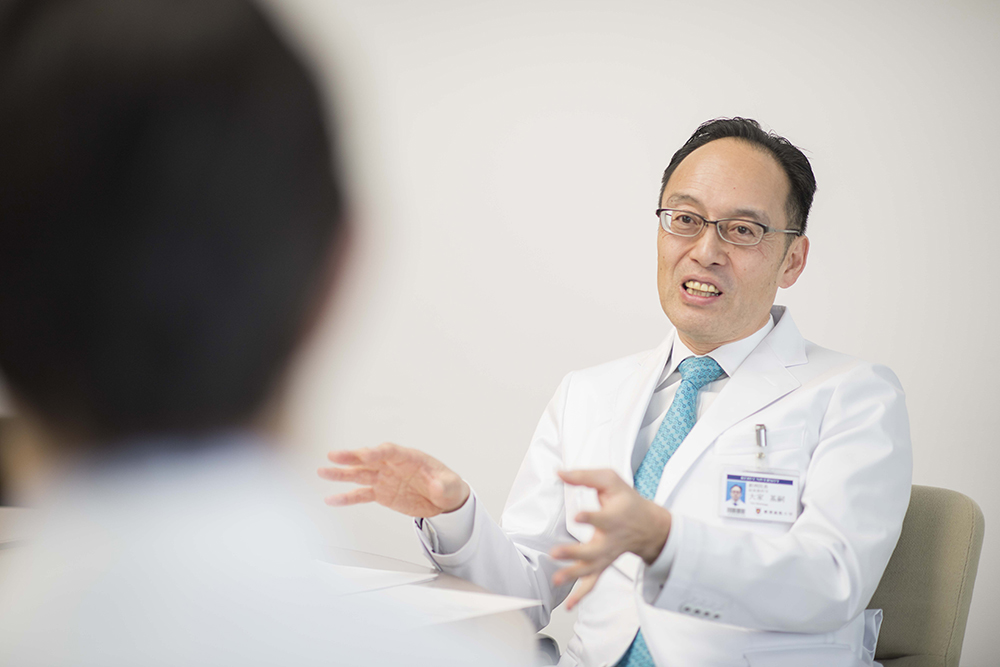
大家:竹内先生の研究分野であるリウマチについても少しお伺いしたいと思います。がん以外の分野でいうと、リウマチは非常に患者数の多い疾患ですよね。
竹内:世界の医薬品の売り上げ(2014年)トップ10の中の4つは、リウマチの薬です。1位はアダリムマブ、3位はインフリキシマブ、4位はエタネルセプトでいずれもTNF-αをターゲットとした、バイオ医薬品です。1980年代くらいからそういった分子標的薬の基盤となる研究成果が、海外では少しずつ出始めました。病気の原因を分子レベルで解明した成果を応用して、その分子のみを標的として効率よく、副作用をより抑えながら、作用するように設計された薬ですね。
その頃、私が何をしていたかというと、1985年前後にアメリカのハーバード大学に留学し、ヒト免疫学を学んでいました。モノクローナル抗体を使って、患者さんの体の中でT細胞・B細胞やNK細胞などの免疫細胞がどう動いているのかを研究していました。抗体をあくまで病態解析のツールとして使っていたんです。ところが、その頃、実はアメリカの研究室では、抗体をもう治療用とで開発していたんです。私には当時そういう発想はまったくありませんでした。
アメリカから帰国後、私は埼玉医科大学で、接着分子(*)を始めとする様々な抗体をつくって、患者さんの細胞を調べていました。1994年に研究が完成して、Journal of Clinical Investigation (JCI)に、接着分子VLA-4 (Very Large Antigen-4, 別名インテグリンα4β1)が血管炎では発現量が多くなっているという結果を発表したのですが、アメリカのグループはその時にはもう、その標的分子を特許申請してあって、開発した抗体を多発性硬化症の患者さんの治験に使い始めていたんです。アメリカは日本の20年先を行っているんですよ。
大家:日本と海外の文化や、医学界における環境の違いが如実に表れていますね。
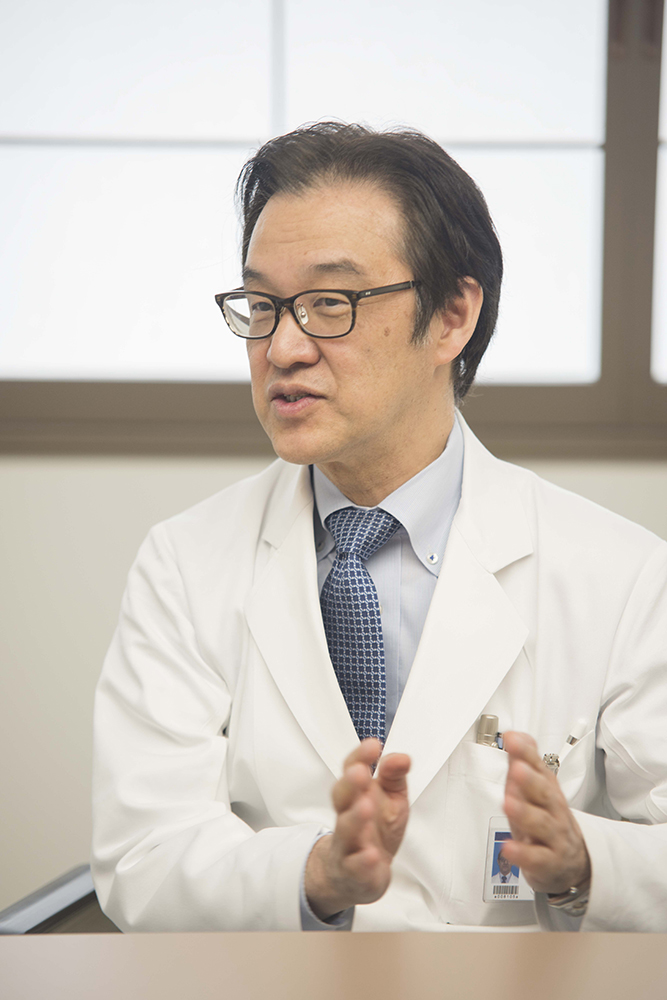
竹内:そうなんです。私が埼玉医科大学でまさしくVLA-4の研究をいわゆるトップジャーナルに論文発表して満足していた時に、インフリキシマブを世界に展開したいので日本でもこの治験をやらないかという話が来たんです。インフリキシマブというのは関節リウマチに対する薬で、1993年にそのもとになった、cA2という抗体に関して臨床試験が行われ、94年からはイギリスで二重盲検法試験が行われました。そして、エビデンスの積み重ねの後、98年に薬として承認されました。イギリスからの問い合わせには大変驚き、ここまで医学研究が進んでいる世界に自分が身を置いているのだなと痛感しました。当時、埼玉医科大学の私の上司である安倍達先生がその治験を受けて、私がそれを手伝いました。
当時、行政には、がんでもない患者さんに、こんな高価で危険な薬を使うんですかと言われましたね。命を長くするなら理解できますが、亡くならない病気の患者さんに、抗体なんていうよく分からないものを、と。抗体は、当時の薬事法で全く想定されていなかったので、とても手当てできない、と言われました。日本の製薬メーカーにも、コストが合わないからこんなもの薬にはならないと断言されました。心良く協力してくれる会社が少なく、大変でしたね。
大家:今振り返ると、隔世の感がありますね。
竹内:そうですね。
医師に必要な視点・スキルとは

竹内:薬の開発に関しては、ネイチャーやサイエンスに載るような論文や基礎医学の素晴らしい成果が、臨床研究の実用化に向くとは限りません。いい論文と、臨床のためのいいシーズは、まったくの別物ですからね。
大家:そのとおりですね。
竹内:画期的な新しい基礎研究でも本当に臨床に応用できるかどうかは、基礎の研究者だけでは、絶対にわからない。やはりトランスレーショナルリサーチを経てシーズから臨床開発に進んでいく時の目利きには、その疾患領域のエキスパートすなわち臨床家が入らないとダメなんです。
大家:そうですね。その視点は持っておかないといけませんね。あと、これからの医師に必要なスキルはなんでしょうか。
竹内:やはり英語ですね。国内だけでシーズから臨床開発まで持っていく場合にはいいのですが、グローバル展開をしようと思うと、国際的なネットワークが必要になります。それにはコミュニケーションツールとして英語が必須になってきます。英語でこちらの状況を説明できて、且つディスカッションもできることが望ましいですね。
大家:でも、英語をうまくしゃべる必要はないんですよね。
竹内:うまくしゃべる必要はまったくありません。英語を上手に話すことが目的ではなくて、お互い説明できて、理解しあえることが目的ですからね。
大家:大切なのは場数を踏むことですよね。やはり耳を慣らさないといけないですし。僕らもアメリカに行くことがありますが、結局みんな多かれ少なかれ恥をかくんですよ。でも、皆最初はそんなものだから、大丈夫、心配するな、まずやる! の気持ちが大切ですよ。
竹内:やるしかないですからね。
大家:あと、私がいつも心がけていることで、若い医師にも伝えていることがあるのですが、患者さんが自分をどう見ているか、という視線を想像することが医師には必要だと思うんです。例えば、初診の時、患者さんはすごく不安に思っているはずです、どんな先生だろうと思っているに決まっています。でも診察を受けて、すごく親切で丁寧だったら、きっと「あぁ来てよかった」と思ってくれますよね。そういう、相手の気持ちを考えることが大切だと私は思うんです。
竹内:そうですね。そういう想像力は大切です。自分から垣根をつくってしまうとそれもうまくいきません。海外とのコミュニケーションも同じだと思いますよ。
大家:なにごとも壁をつくってはいけないですよね。徹底して壁を取らないといけませんね。
竹内:壁をとれるかどうかが、すべてのカギですね。かなりハードルの高い課題だとは思います。
大家:そのとおりです。若い医師の方には、特に意識していただきたいですね。竹内先生、ありがとうございました。
※接着分子:コラーゲンなどの細胞の外にある基質に、細胞を接着させるタンパク質。細胞外の環境に応じて細胞のふるまいを変化させる働きがあるので、多くの疾患に関係する。
対談後記
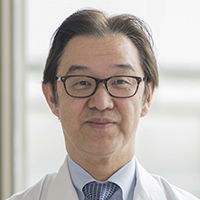 今回インタビューを受け、自分自身の経験を振り返ったときに、これからの世代の先生方には、日本国内で完結しないで、もっと国際的なネットワークをつくってグローバルにも活躍して欲しいと感じました。慶應には、伝統的に基礎医学と臨床医学が緊密に連携して、本当に患者さんのためになる医療を展開しようという理念があります。実際のところこの理念を具現化するのは大変に困難な道のりなのですが、自分自身で作った壁の中で満足せず頑張って欲しいと思います。今回は、インタビューの機会を頂き有難うございました。
今回インタビューを受け、自分自身の経験を振り返ったときに、これからの世代の先生方には、日本国内で完結しないで、もっと国際的なネットワークをつくってグローバルにも活躍して欲しいと感じました。慶應には、伝統的に基礎医学と臨床医学が緊密に連携して、本当に患者さんのためになる医療を展開しようという理念があります。実際のところこの理念を具現化するのは大変に困難な道のりなのですが、自分自身で作った壁の中で満足せず頑張って欲しいと思います。今回は、インタビューの機会を頂き有難うございました。
竹内 勤 教授
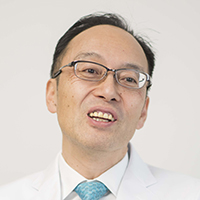 今回のインタビューで特に頷かされたのは、臨床医学の大切さですね。たくさんの患者をしっかり診ることでしか培われない臨床家の観察力の重要性を常々感じているのですが、私の専門領域とは全く異なるリウマチという分野の竹内先生も同じ意見をお持ちでした。今後、医学はますます進歩していくし、社会からの病院への要請もますます高まっていく状況で、病院長の任は大変な重責だろうとお察します。我々のセンターも協力を惜しみませんので、竹内先生のリーダーシップのもと病院全体で力を合わせて素晴らしい病院をつくって行きたいと思います。
今回のインタビューで特に頷かされたのは、臨床医学の大切さですね。たくさんの患者をしっかり診ることでしか培われない臨床家の観察力の重要性を常々感じているのですが、私の専門領域とは全く異なるリウマチという分野の竹内先生も同じ意見をお持ちでした。今後、医学はますます進歩していくし、社会からの病院への要請もますます高まっていく状況で、病院長の任は大変な重責だろうとお察します。我々のセンターも協力を惜しみませんので、竹内先生のリーダーシップのもと病院全体で力を合わせて素晴らしい病院をつくって行きたいと思います。
大家 基嗣 教授
