金子 祐子 准教授(リウマチ・膠原病内科)
大家基嗣によるリレーインタビューの最終回。2014年の臨床研究推進センター立ち上げから5年。慶應義塾大学病院の「変革」の要として、現在の臨床研究推進センターに至るまでには、たくさんのプロフェッショナルの力がありました。
日々、真摯に患者さんに向き合って臨床の知見を積み、現在の医療現場で解決できない問題と出会い、なんとかしたいと強く願って基礎研究や臨床研究に邁進してきた医師たち。医師の想いを具現化すべく臨床研究をサポートしてきた支援部門のスタッフたち。
最終回は「先人に聞く医師主導治験」シリーズ。変革のマイルストーンとなった2011年の「早期・探索的臨床試験拠点整備事業」の時代から免疫難病分野の臨床研究を牽引してきた、慶應義塾大学病院 リウマチ・膠原病内科の金子祐子(かねこ・ゆうこ)准教授 をゲストに迎え、臨床研究のこれまでとこれから、ご自身が手がける最新の臨床研究について聞きました。
Profile
金子 祐子 准教授慶應義塾大学病院 リウマチ・膠原病内科
大家 基嗣 教授
慶應義塾大学病院・副病院長
慶應義塾大学医学部・泌尿器科学教室・教授
慶應義塾大学病院・臨床研究推進センター・広報部門長
※所属・職名等は取材時のものです。
疑問の声を背にスタート。リウマチ内科と共にした15年
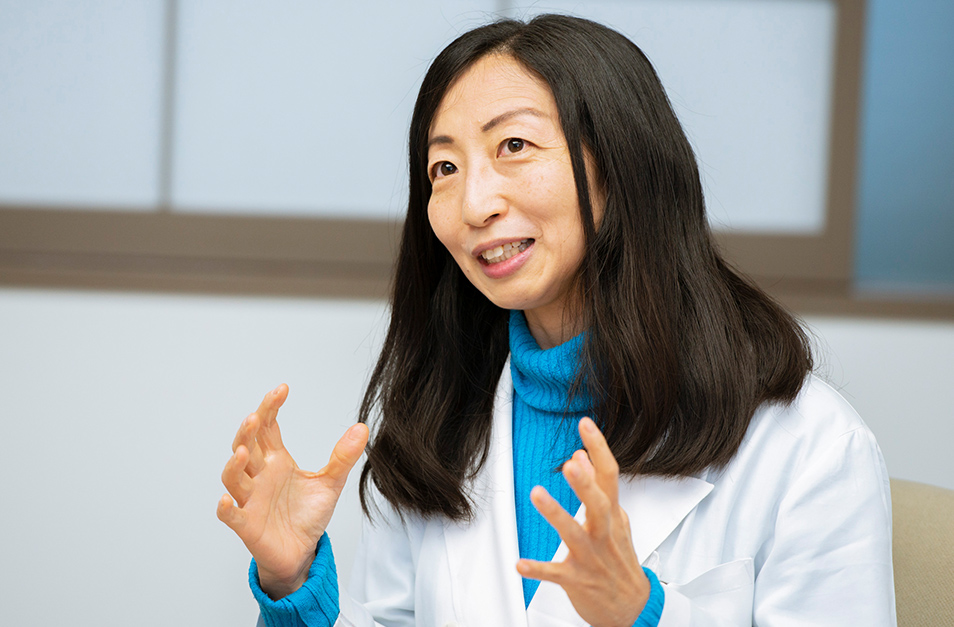
大家教授(以下、大家):慶應義塾大学病院と臨床研究推進センターが「今」に至るまでには、いくつかのマイルストーンとなる出来事がありました。2011年の「早期・探索的臨床試験拠点整備事業」の採択で、慶應義塾大学病院が免疫難病分野の医薬品の選定拠点となったことも、その一つですね。金子先生は、この取り組みに深くたずさわられておられ、慶應義塾における臨床研究の歩みを語るに欠かせない存在です。
金子准教授 (以下、金子):ありがとうございます。
大家:たくさんお聞きしたいことがあるのですが、まず、なぜリウマチ膠原病内科の医師になろうと思ったのか。その辺りから、ぜひ話をお聞かせください。
金子:もともと免疫という全身に関係する仕組みに興味がありました。また、臨床的には、全身の臓器を横断的に勉強できる内科に進みたいと思っていました。リウマチ膠原病は免疫異常に起因する病気で、全身の臓器を障害します。その点で最も内科らしいと感じてリウマチ・膠原病領域に進むことを希望しました。
大家:しかし先生が入局された頃は、今ほどリウマチの薬がなかった時代かと思います。慶應義塾の医学部名誉教授も務められた故・本間光夫先生がリウマチ・膠原病の第一人者で、とても魅力的な授業をなさっていました。私も受講して魅了されましたが、当時は治療法が痛み止めとステロイドしかなかったように思います。
金子:はい。リウマチ・膠原病領域ではそういう時代が長く続いてきました。
大家:シクロフォスフォスファミド(免疫抑制剤)もありましたが、非常に限られた治療薬でしたよね。
金子:そのとおりです。当時のリウマチ・膠原病は、ステロイドや有効性の低い免疫調整薬、毒性の強いシクロフォスファミドに頼らざるをえない状況でした。膠原病ではまだその傾向がありますが、関節リウマチにおいてはブロックバスターと呼ばれる最初の生物製剤が、日本で使用可能となったのが2003年です。私がリウマチ内科を専門に決めたのがちょうどその年のことで、周りからは「リウマチ内科に入って何するの?」と言われるほどでしたが、そこから治療がぐんぐんと進歩し、この15年でパラダイムシフトがおきました。今は、患者さんが完治したかのような日常生活を送れる。そのくらいのところまで治療できる環境になってきました。
大家:リウマチ膠原病治療の変革期と金子先生の医師人生が、ぴたりと重なっていますね。まさにリウマチ内科と共に悩み、考え抜きながら、新しい治療を築いてこられたのですね。
患者さんの「バリュー」と向き合う医療へ

大家:最新の治療とともに歩んでこられた先生ですが、臨床研究の歩みは診療とはまた別物だったのではないでしょうか。金子先生が臨床研究に興味を持たれたきっかけを教えてください。
金子:リウマチ内科の入局当初は、自己抗体が産生されるメカニズムの研究に取り組んでいたのですが、そのうちに「自己抗体を臨床にどう生かせるか」に興味があることに気づきました。ちょうどその頃、臨床研究推進センターの前身であるクリニカルリサーチセンターが立ち上がり、特別研究助教を拝命する機会に恵まれました。このクリニカルリサーチセンター時代に、現在、衛生学公衆衛生学教室の教授でいらっしゃる武林亨先生や当時センター長の佐藤裕史教授に非常に熱心に指導いただき、臨床研究の面白さを知ることになりました。
大家:クリニカルリサーチセンターの発足は、慶應医学部の歩みの中でも非常に大きなマイルストーンになりましたね。あの頃の佐藤教授や武林先生のご貢献は、評価してもし過ぎることはないくらいです。あれから13年が経とうとしていますが、万感の思いです。
金子:本当におっしゃるとおりですね。佐藤教授はアカデミアに来られる以前は製薬企業にいらしたので、世界の製薬会社の標準的な考え方等、私たちの知らない世界を見ていらっしゃっていました。しかも、それを惜しみなく与えて教えてくださるので、本当にたくさんの学びや気付きがありました。
大家:研究開発のための競争的資金も多方面から獲得し臨床研究を推進くださいました。金子先生は、そんな佐藤教授や武林先生のすばらしい教えを一身に受けられたのですね。その後、オックスフォードに留学されていますが、そのお話もぜひお聞かせください。
金子:ずっと留学したいと思っていたのですが、それなりにいろいろな仕事を抱える中できっかけやタイミングを見つけられないでいました。私がリウマチ内科に再配属された2009年ごろ、当科教授になられた竹内勤先生が「そんなことを言っていたら一生留学できない。自分が行くと決めたら、すぐに行ったほうがいい」と、背中を押してくださいました。
大家:竹内先生はグローバルで活躍されているので、臨床研究や治験情報に詳しく、ご自身でも基礎研究をなさっていたので、学びに対して大変ご理解が深いですよね。オックスフォード大学では臨床研究を学ばれたのですか?
金子:はい。活発に活動しているチームに仲間に加えていただき、特に患者立脚型アウトカム(Patient Reported Outcomes:PROs)を評価する研究に主体的にかかわりました。それまでの臨床研究では、検査数値などの客観的指標が適切な指標であり、患者さんの主観的評価は科学的ではないと考えられてきました。しかし少し前から、欧米を中心に、本来治療は患者さんのためのものですから、治療評価に患者さんの主観的評価、例えば痛み、痒み、外観等の指標を積極的に取り入れるべきという考え方が発展してきています。患者さんの評価は客観的評価と同等に信頼性の高い評価です。PROsは、今、私のメイン領域になっています。
大家:PROsは、ようやく最近、日本でも注目されるようになってきましたね。世界的に見るとヨーロッパが非常に進んでいる印象です。
金子:そのとおりですね。
大家:「エビデンス・ベースド・メディスン」※1 からの流れで、その次に注目されているのが医療技術評価。医療技術評価は費用対評価の視点もあれば、PROsの視点もあります。患者さんにとっての価値にフォーカスしたものがPROsですね。今ではそれらをすべて包括した評価視点が注目されています。
金子:はい。「バリュー・ベースド・メディスン」と呼ばれています。
大家:患者さんにとっての「バリュー」を起点にする医療という意味ですね。今から約7年前、日本が患者さん自身の価値に基づくという視点に目覚めたころ、すでに金子先生はPROsに取り組まれていたとは、まさに先駆的ですね。
金子:患者さんにとっての「バリュー」とは何か、そのために私たちは何をすべきか。これからも問い続けたいと思っています。
成人Still病に対する治療法の開発 -良いチーム関係を経て、さらに良い関係性を築く

大家:約1年にわたるオックスフォードでの研修期間の後、慶應に戻られてリウマチ内科の講師になられています。
金子:はい、2013年のことです。その後、成人発症スティル病※2の治験の代表医師として、医師主導治験を統括することとなりました。前任の亀田秀人先生がプロトコール作成に着手されていましたが、東邦大学に教授としてご異動された後、引き継ぎました。
大家:慶應義塾では「早期・探索的臨床試験拠点整備事業」の枠組みとして第一号の医師主導治験ですね。どのようなご苦労があったのでしょうか。
金子:成人発症スティル病は関節リウマチの親戚のような病気ですが、特徴的な症状として慢性関節炎や皮疹、高熱が出ることがあげられます。リウマチ因子や抗核抗体などの自己抗体は陰性で、自己炎症性疾患と考えられています。
疾患の病態にはIL-1やIL-6、IL-18といったサイトカインが重要であることは以前から知られており、関節リウマチの治療薬であるIL-6阻害薬トシリズマブがスティル病に効くのではないかというレポートは散見されていました。しかし、成人発症スティル病は希少疾患で、当時日本に1000人前後と言われていたので企業は治験に取り組みにくい状況でした。
大家:そうでしょうね。
金子:ならばもう、医師主導で治験をやるしかないというのが私達の科の思いでした。
大家:しかし、それだけ患者さんが少ない希少疾患となると、治験にご協力いただける患者さんをどうリクルートするかという部分が、非常に難しかったのではと推察します。
金子:はい。最初は慶應義塾大学病院のみで行う予定でしたが、お察しの通り、治験に必要な人数が集まりませんでした。そこで、なんとか資金を捻出し、全国8施設の主要な大学病院の先生方にご協力をお願いしました。また、Webサイトに募集告知を載せたり、メディカル雑誌の編集部に情報を持ち込んで医師主導治験の特集記事内で慶應病院の取り組みに触れてもらうなど、さまざまなアプローチを試みました。
大家:奔走されたのですね。この治験は終了したのですか?
金子:はい。二重盲検試験(Double Blind Trial:DBT)を終了し、現在、適用拡大の承認を取るべく申請中です。承認が下りるまで長期試験は継続中です。
(※その後、2019年5月にトシリズマブの成人スチル病に対する効能・効果追加が、厚生労働省により薬事承認されました。)
大家:それはすばらしいですね。私も橋渡し研究の枠組みで医師主導治験を実施しましたが、その際、臨床研究推進センターの臨床研究支援部門のみなさんがプロトコールや書類の準備を全面的にバックアップしてくれて非常に助けられました。おかげさまで患者さんのリクルートに専念することができたのですが、金子先生はいかがでしたか?
金子:私も当時在籍されていた菊地佳代子さんや阿部貴行先生、現在も支援いただいている藤木勇人さんをはじめとするみなさんに、多大なご支援を頂きました。
大家:臨床研究推進センターを含め、良いチームづくりができたんですね。
金子:はい。嫌な顔一つせず、夜中にメールしてもすぐにご返信頂いたり、PMDA(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency;独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の審査に関しても相談から同行、面会まで同席して頂いて、とても助けられました。
大家:その臨床研究推進センター・臨床研究支援部門のみなさんから、支援体制に関するフィードバックを聞かせてほしいとリクエストが来ています。いかがですか?

金子:私にとって初めての医師主導治験だったので、正直、スタート時は右も左もわかりませんでした。企業治験と異なり自分が主導する側になると本当にやるべきことがたくさんあり、サポートはとてもありがたかったです。さらに良いチームになるため、という観点でお話ししますと、私たち医師は医療現場で診断や治療に邁進していますので、いざ臨床研究・臨床試験に臨むとなると、座学だけではわからないリアルな部分、いわば"さじ加減"がわからないことがあります。そういう点をTipsとしてアドバイスいただけると、一層心強いなと思います。具体的には、本にはこう書かれているけれど、企業治験ではこうやって対処するのが一般的ですよ、などのサジェスチョンがいただけるとうれしいですね。
大家:なるほど。支援する側としては当たり前のように認識していることが、実は、医師にとっては、新たな"気づき"になることがあるわけですね。
金子:はい。医師が教科書的な知識で医師主導治験に臨むケースは特にそうだと思います。細かい部分で悩んでしまうことがよくあるので、具体的な事例を踏まえながらご相談に乗って頂けると、医師主導治験に初挑戦する人の力強い後押しになると思います。
大家:貴重なご意見、ありがとうございます。特に多職種の方でチームを組む場合は、ある分野に特化している専門家の当たり前が、当たり前でない場合がありますからね。例えば、この略語が何を指しているかなど、ごく入り口の部分で立ち止まってしまうことだってある。特に最初の段階は、もう少し噛み砕いた説明や踏み込んだサジェスチョンを必要としている人も多いかもしれません。
金子:はい、そう思います。
大家:しっかりセンターにフィードバックし、良いチームづくりを後押ししたいと思います。やはり、チーム内に治験の進め方や対応に慣れた方がいると心強いですよね。こういった方々のおかげで、若い先生も安心して医師主導治験に臨める環境が生まれていると思います。ぜひ若い先生方に積極的に医師主導治験に参加してほしいです。
金子:そうですね。怖がらずに主体的に臨めば、勉強しながら自分の成長を実感できますし、いいものが作れていることを日々感じることができると思います。
