第2回再生医療等支援部門座談会
臨床研究の現場から
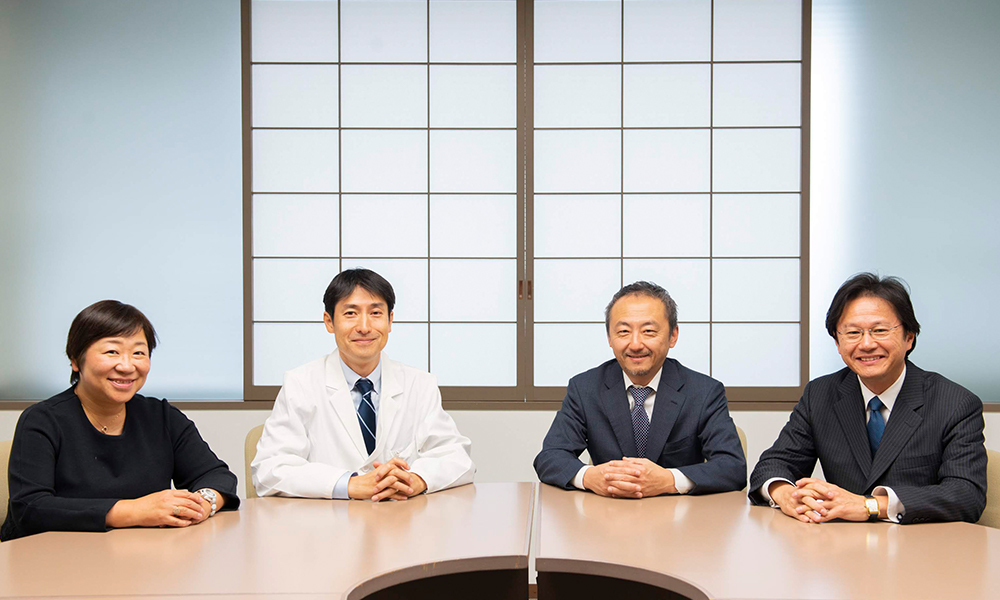
Profile
中村 雅也 教授
慶應義塾大学病院・臨床研究推進センター・再生医療等推進委員会委員長
榛村 重人 准教授
慶應義塾大学病院・臨床研究推進センター 再生医療等支援部門長
許斐 健二 特任准教授
慶應義塾大学病院・臨床研究推進センター 再生医療等支援部門 副部門長
大村 光代 特任講師
慶應義塾大学病院・臨床研究推進センター・広報部門長
再生医療のニーズの高まりから
立ち上がった「再生医療等支援部門」

大村:慶應義塾大学では、再生医療の研究と実用化に以前から取り組んでおり、2019年4月には慶應義塾大学病院臨床研究推進センターの一部門として「再生医療等支援部門」が開設されました。本日は、この再生医療等支援部門に関わる先生方にお話を伺いたいと思います。まず、設立の経緯、組織構成、研究内容などについてお話しいただけますか。
榛村:再生医療に対して社会の期待とニーズが高まっているのはもちろんですが、私自身も2014年の「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(以下、再生医療等安全性確保法)」施行前の「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」の頃から角膜の再生医療研究を行っており、研究を最終的に医療として患者さんに届けるところまでを支援する部門の必要性を痛切に感じていました。
また、慶應義塾大学病院は、iPSを含む再生医療の関東における拠点としての責務を担っており、研究開発の加速も急務となっていました。
このような、再生医療に関する社会的ニーズや研究者側のニーズなどに対応するために、再生医療等支援部門は立ち上がりました。
許斐:組織構成については、私からお話しさせていただきます。
再生医療等支援部門は業務を3つのユニットに分けて行っています。
まず「RM支援ユニット」は研究シーズの開発支援を担当し、研究費の獲得支援も含め研究シーズの開発段階に応じた幅広い支援を行っています。
2つ目の「RM管理ユニット」は、法令等の規制に対する適切なアドバイス、必要となる各種資料作成支援、管理を行っています。再生医療では、「再生医療等安全性確保法」「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)」という2つの法律を理解していないと、実際に患者さんに届けるところまで進めることは難しいため、このユニットの存在は非常に重要です。
3つ目の「細胞調整等支援ユニット」では、実際に人に投与するための細胞を製造(細胞培養加工)する施設の提供や、製造に関わる業務の支援を行います。これらの3つのユニットが再生医療に対する支援を推進しています。

大村:再生医療等支援部門の設立前は、同センターのトランスレーショナルリサーチ(TR)部門や臨床研究支援部門が再生医療に関連するプロジェクトの支援を行ってきました。しかし、薬事的な法令に従って開発を進めていくには再生医療分野の経験者が必須と感じていました。今後は、RM管理ユニットが中心になって推進していくことになりますか。
許斐:開発そのものの支援はRM支援ユニットが担いますが、「薬機法」や「再生医療等安全性確保法」等に対する対応、特に再生医療等提供計画等に関する助言等はRM管理ユニットが中心になって支援していくことになります。
大村:研究プロジェクトそのものの支援をRM支援ユニットが担い、その周辺のさまざまな環境整備をRM管理ユニットがサポートし、実際のものづくりに関しては細胞調整等支援ユニットが担うというイメージですね。
許斐:はい、まさにそのイメージです。
ユニットごとに異なる人材
育成もリクルートも多様

大村:医薬品や医療機器については法令も整備され、開発のプロセスもある程度決まっていますが、再生医療に関してはまだそこまでは整備されていませんから、運営もいろいろ苦労されておられるでしょう。
榛村:横断的に全体を把握できる人材がいない状況ですから、まずは人材の育成が1つのミッションだと考えています。業務を遂行できる人材はすぐに育つわけではありません。現行のプロジェクトを推進しながらどのように支援していくかが、今、最も重要だと感じています。
許斐:そもそもARO(Academic Research Organization)の人材確保そのものが難しいという問題があります。特に再生医療は新しい分野ですから、研究開発の初期段階、ヒトへの投与、最終的には製品化まで幅広いノウハウを備えた人材はなかなかいないというのが実情です。一方で、再生医療の研究では医師や研究者が直接関われる部分が比較的多くあり、ここは医薬品等とは異なる特徴だと思います。環境整備、サポート体制ができてくれば、現場の研究者にとっては大きなモチベーションにつながっていくと考えています。
大村:実際に、どのような人材が必要か、どのような経験を持っている人、あるいはどういう教育が必要なのか等、具体的なアイディアや提案はありますか。
榛村:今はさまざまな領域で専門化が進んでいますが、あまりに専門領域に特化しすぎると全体像が見えない、向かっている方向がずれていると結局、実現に向かわないのではないかという懸念もあります。むしろ、ジェネラリストが必要ではないかと思っています。許斐先生もお話しされたように、医師である研究者自身が研究成果を直接患者さんに届けることが多いため、研究開発のプロセスやエビデンスの理解に加え、関連する法律を理解しながら全体の把握ができる人材を少しずつ増やしていく必要があると思います。
もう1つ重要だと思っているのは「連携」です。研究開発は、医師だけでなく、多くの関係者と協力して進めていくことが非常に重要です。したがって、コミュニケーション能力の高い人材が求められます。

許斐:先ほど3つの支援ユニットで構成しているとお話しましたが、それぞれのユニットで必要な人材は異なります。
例えば、開発の初期段階から研究費の獲得等をしながら進めていくRM支援ユニットは、対象研究シーズこそ再生医療等製品や特定細胞加工物になりますが、医薬品や医療機器の開発とあまり大きな違いはないのではないか。そこで、この担当者はOJTによる経験の蓄積が重要ではないかと思います。
RM管理ユニットは、規制当局にいた経験がある方で、今後企業やアカデミアで仕事をしたいという人材を取り込み、一緒に開発していく方法があるのではないかと思います。
細胞調整等支援ユニットは、実際に細胞を加工して製品にしていく業務ですが、これに関する法律も発出から5年程経っており、製造経験のある人材が世の中に相当数存在するはずですから、アカデミアで仕事をしたいという人材をうまくリクルートできればいいと思っています。規制当局ともコミュニケーションを取りながら開発をすすめて、経験を蓄積しつつ人材育成をしていくというのが現実的と考えています。
学外の研究者からも
期待される高度な支援

大村:中村先生は、慶應義塾大学で再生医療研究の運営に総合的に関わっておられますが、慶應における再生医療等製品の研究は今後どういう方向性で進めていこうと考えていらっしゃいますか。
中村:今回この座談会に参加させていただいたのは、私が再生医療等支援部門と緊密に連携を取っている再生医療等推進委員会の委員長という立場にあるからではないかと思っています。
先ほどもお話が出ましたが、今回、再生医療等支援部門新設の引き金になったのは、慶應義塾大学病院がAMED(日本医療研究開発機構)の再生医療臨床研究促進基盤整備事業に「東日本におけるiPS細胞等臨床研究推進モデル病院の構築」の課題にて採択され、日本、特に東日本における再生医療を推進するプラットフォームになって欲しいと言われたことだったと思います。慶應には再生医療に関するいろいろなシーズがあり、研究開発が進んでいますが、それらは臨床研究推進センターが中心になって支援しています。この仕組みを活用し、学外のシーズも同様に支援し、社会実践に向けて推進することを、しっかりとサポートし加速して欲しいということですね。
毎月開催されている再生医療等推進委員会では、再生医療等製品についてどのように進めていくべきかを議論しています。
課題はたくさんありますが、まずは成功例を出していき、その支援の過程の中でわれわれ自身が学んだことを形にしながら、ノウハウをつくり上げていく。さらに経験値から得られたシステムや方法論等を学外の関連施設と共有する、あるいは学外機関と連携することにより、日本における再生医療の裾野を広げていけるのではないか、その中核的な役割を慶應が担うことになると思っています。
大村:慶應義塾大学は、AMEDの橋渡し研究支援拠点に選定されており、私もTR部門として日々橋渡しプロジェクトに携わっていますが、学外の機関からの申請応募が増えてきています。その理由の1つとして、「再生医療等製品」について、慶應ならいろいろな経験を持っているし、プロジェクトも前に進めてくれるだろうという話をよく聞きます。
さらに、臨床試験まで慶應義塾大学病院が中心になって実施してくれるという期待を持って応募してくださる先生がたも多いように感じます。そういう意味でも、1つのモデル事業の拠点となって運営していくのは、非常に重要なことだと感じます。再生医療等推進委員会では、どのような議論をされていますか。
中村:基本的には新たな仕組みを作ろうとしています。まずは内規を作成し、関係者がその内規に沿って、どういったミッションを担っていくかというところから議論を始めています。それと同時に、推進委員会は学内外のシーズの研究開発が、どのように進められているかについての情報を共有する場でもありますから、研究課題で困っている事項について知恵を出し合いながら方向性を定めていく議論をしています。この議論の結果をしっかりと現場に還元し、実際に研究課題を支援していただくのが、再生医療等支援部門だと思っています。
